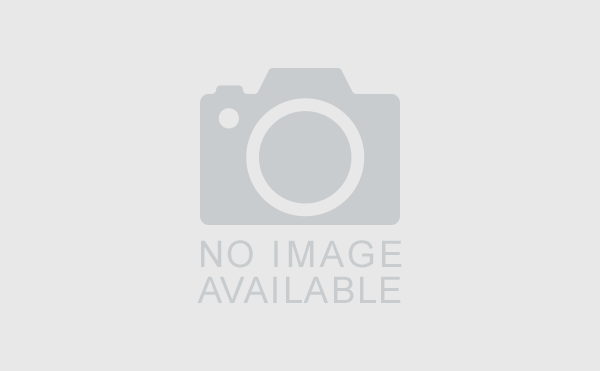GPLが契約と誤解される理由?
※『「契約」について』の続編になります。
なぜ、多くの人がGPLは契約と思いたがるのか、不思議でした。
1. 契約と言ってしまう理由の一つ
だいぶ昔のある日、多摩地区のメーカーでセミナーさせていただいた後、受講された技術者の方の一言でヒントをいただきました。
なぜ、GPLを契約と考えてはいけないか、やっと分かった。契約は、単に『守らなければならないもの』としか考えていなかった。
確かに、「契約だから守りなさい」と言われ続ければ、「契約は守らなければならないもの」という認識が増長して、「守らなければならないもの=契約」という認識が生まれてしまったのではないかと想像できます。
「GPLは守らなければならないもの」ということを強調したくて「GPLは契約だ」と言っていた人もいたかもしれません。
'GNU GENERAL PUBLIC LICENSE'をバージョン3では「GNU 一般公衆利用許諾書」と訳した(2018年)八田真行氏も、バージョン2では「GNU 一般公衆利用許諾契約書」と訳してしまっていました(2002年)。
※八田氏自身、GPLv3を紹介する講演で、GPLv2の契約と訳してしまったことを「ちょっと勇み足」というようなことを発言されていました。
GPLが契約でなくても、著作権法に基づいているのでしたら、法遵守しなければならないのは当たり前です。「守らなければならないもの=契約」という認識がトンデモ方向に飛んでしまって、「契約は守るもの。法律は破るもの」とでも認識してしまっている人もいるのかもしれません。
2. 契約は絶対に守らなければならないものか
先に紹介した樋口先生の御本に、少々衝撃的な文言がありました。
「契約を破る自由」…自由といっても自由勝手ということではなく、「損害賠償責任だけは果たした上での自由」だという点です。しかし、それでも契約を破っていることには違いありません。
…
アメリカで最も著名な法学者であり裁判官であったホームズ(Oliver Wendell Holmes, Jr.)…彼は、契約法において法と道徳との混淆が行われていることを強く非難し、契約違反は悪ではないと明言しました。英米法上、契約を結ぶということは、契約を履行するか損害賠償を支払って履行をやめるかの選択権を持つことを意味するにすぎないというのです。それは債務者の権利であり、債権者の権利ではない、と。
…
コロンビア大学のファーンズワース(E. A. Farnsworth)教授…彼もまた次のようにいうのです。「やや驚かれるかもしれないが、アメリカ契約法上の救済制度の目的は、債務の現実的履行の強請ではない。……問題は、どうやって債務者に約束を守らせるかではなくて、どうしたら人々が契約関係に入るのを促進できるかである。……ともかく、誰もが認める契約締結の自由とならんで、契約を破る相当の自由(a considerable freedom to break them, them=contracts)が同様に認められているのである」。
このようにアメリカの2大権威を持ち出したのですが、それでも「契約を破る自由」とう考え方にはついて行けないという人が、少なくなかったようです。…契約を破る自由も、アメリカですら誰にとっても常識というわけではなかったのです。
樋口範雄 著『はじめてのアメリカ法(補訂版)』有斐閣、2013、P75-79
たぶん、契約書の内容を具体的に作成する実務を、特に、海外企業との契約の実務をされたことのない方は、まさに、「法と道徳との混淆」(玉石混淆の混淆(こんこう)です)してしまっている人が少なくないのではないでしょうか。十数年前の記事で「(GPLが)著作権法に基づくなら、なおさら契約と考えるべき」とのコメントをいただきましたが、当時は、どういう論理なのか全く意味不明でしたが、これもコメント者が「法と道徳との混淆」をしていて、「(GPLが)著作権法に基づくなら、なおさら[守らなければならないもの]と考えるべき」という意味で契約という用語を誤用していたのかもしれませんね。どうも、言葉の意味を確認せずに、ご自分のイメージで誤用されている方が少なくないのかもしれません。
一方、10年ほど前のことですが、この「契約を破る自由」の話を会社の人にしたとき、意外にも、特に驚いた様子もなく当たり前の顔をされました。実際に契約内容を作成する方にとっては、履行できなかったときの損害賠償などを検討し盛り込むことなど当たり前だったのかもしれません。
これらのことから、「守らなければならないもの=契約」と考えること自体、妥当ではないことがお分かりいただけるのではないでしょうか。
3. 弁護士先生が「GPLは契約」と解説する理由の推測
弁護士先生にGPLを解説してもらうことが多かった時期がありました。理系の人間というか業界の人の多くは、弁護士先生は法律の専門家で、正しい解説をしてくれるものと考えていました。
あるセミナー後、弁護士先生に「なぜ、GPLを契約と考えるのですか?」と聞いたことがあります。そのときの応えが
弁護士だから。
そのとき、「なぜ、弁護士だとGPLを契約と考えるのですか?」と聞けば良かったのですが、なぜかまともに応えてもらえなさそうで聞かなかったので少々後悔しています。
その後、いろいろ推測してみましたが、答えは見つからず、Copilotに聞いてみると、こんな答えが返ってきました。
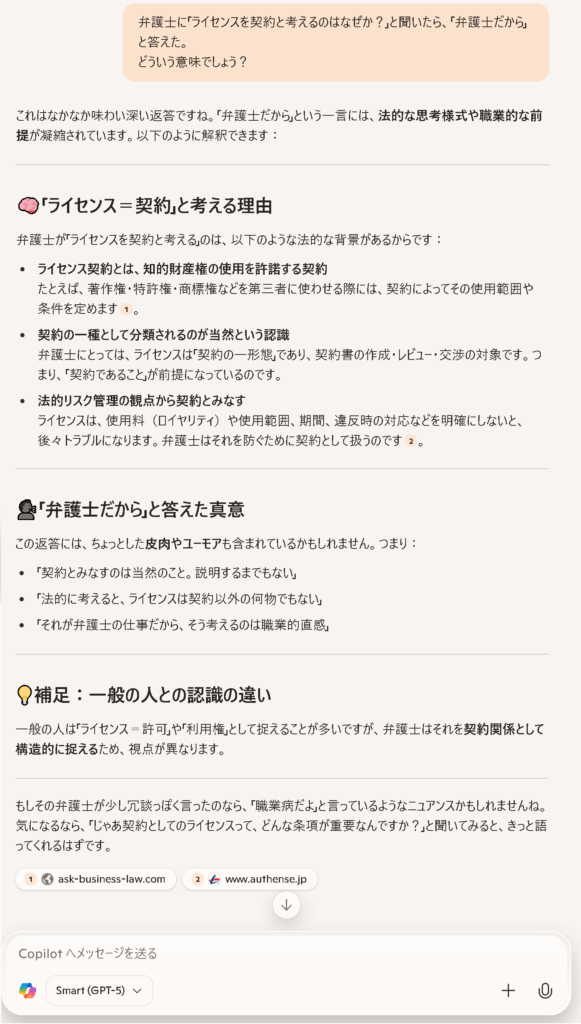
どこまでネタ扱いしていいのかわかりませんが、OSSライセンスのことを弁護士に相談や解説をお願いしたら、デフォルトで契約として扱われると考えた方がよいようで、弁護士に頼むということは契約として扱ってくれと依頼しているようなものと認識したほうがよいのかもしれません。
ウィキペディアによると、明治初期ごろは、弁護士は「代言人(だいげんにん)」と呼ばれていたらしく、依頼者に代わって代弁してくれる人から始まったようです。そして、「民事訴訟では、原告・被告等の訴訟代理人として主張や立証活動等を行」いますが、「刑事訴訟では、弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは適切な量刑が得られるように、検察官と争う」立場です。つまり、契約違反の民事訴訟でなければ、著作権法違反の刑事訴訟では、弁護士は、著作権侵害した被告人の「弁護」をする立場です。
我々一般人からしてみれば、弁護士先生は法律の専門家という認識の方が多いと思います。その法律の専門家が言うことに間違いは無い、と考える人が多いでしょう。でも、先の樋口先生の御本では、以下のように書かれています。
法律の素人は、弁護士が何でも知っていると考えがちです。そんなことはあるわけがありません。六法全書にある法律の条文をすべて知っていると考える人もいます。それは二重の間違いです。そんなことは不可能だという意味での間違いと、条文だけ知っていても法律を知っていることにはならないという意味での間違いです。
さまざまな法律があり、それよりももっと多様な紛争があります。法律家がそれらについて、あたかも症状を聞けばただちに最適の薬を棚から持ってくることができるかのように思うのはまったくの誤りです。それはアメリカでも同じです。ある紛争についての法がどうなっているのかの知識は(前に同種の紛争に関係して)たまたま知っているという場合もありますが、そのようなケースでも常に法は新しくなりますから、前の知識に頼りきることも危険です。
したがって、弁護士にまず求められるのは、症状(紛争)に応じた最新の薬(ルール・法)を探す能力です。検索能力なのです。法について的確な調査能力のある人、これが弁護士です。樋口範雄 著『はじめてのアメリカ法(補訂版)』有斐閣、2013、
P39-40 「弁護士は法律を知っている人ではない」
大学の法学部は、工学部のように細かく学科に分かれているわけではありませんが、やはり、専門分野というのはあるかと思います。工学部情報処理学科卒の人がコンピュータ・ソフトウェアの技術者になれても、コンピュータ・ハードウェアの設計や、ましてや、データセンターの建築設計ができるようには相当の困難があるでしょう。法学部において、著作権法を含む知的財産権関連の法律はマイナーな位置づけのようです。司法試験においても、知的財産権法という試験科目は選択科目であり、選択しないで弁護士になった方もいるでしょう。
※余談になりますが、ある昔の知的財産権の書籍で「知的財産権法は、特許法・著作権法などから構成される」という説明を見かけたことがあります。「知的財産権は、特許権・著作権などから構成される」という説明なら正しいかと思います。しかし、知的財産基本法という法律はありますが、知的財産権法という法律は存在しません。どこから、知的財産権法という言葉が出てきたのかと疑問に思っていたら、どうも、司法試験の科目名として知的財産権法という言葉があるようで、その著者は、司法試験対策本でも無い一般書で、こんな説明をしてしまったようです。
4. 誤解しないために
当たり前のことでしょうが、専門家(と勝手に思っている人)の言うことだからと鵜呑みにせず(そもそも、相手のスタンスを考慮して、依頼の仕方が妥当だったのかもありますし)、自分で考え、納得のいく理由を見つけることが大事かと思います。
2025.9.2 姉崎章博